第33号
定説を問う
~川村孫兵衛と政宗公~
岩沼市市史編纂委員・玉浦郷土史研究会会長阿部俊雄氏に聞く
貞山運河・木曳堀の開削ばかりでなく四谷用水、北上川治水工事など仙台藩で水のインフラを整備した川村孫兵衛。仙台城や仙台の町の建設、仙台の用水確保、仙台藩の石高増嵩など彼の仙台藩への功績は計り知れません。 今回は岩沼市、政宗公、川村孫兵衛など多年にわたって研究されてきた同氏に川村孫兵衛と政宗公についておうかがいしました

川村孫兵衛と政宗公の出会いは?
政宗公と孫兵衛は「(政宗公が)伊達領であった近江国蒲生郡に滞在中、上方にいた伊達政宗からその才能を見出されて慶長6年(1601年)に伊達氏の家臣となった。」(ウキペディア)とあります。
これが定説だと思います。
しかし両者が出会ったのは1596年に起こった慶長伏見地震で倒壊した京都の伏見城を立て直せよとの命が秀吉から発せられ、各地の大名が伏見に滞在していた時なのです。
再建の中心人物は秀吉政権下の五大老のひとりで備前岡山城主の宇喜多秀家でした。
この時全国の築城技術者が参集しました。
長州藩毛利家からは熊谷元直そして川村孫兵衛が来ていました。
この時政宗公と会っていたと思われます。

孫兵衛が仙台藩に来た目的は?
再建には材木ばかりでなく鉄も使いますが大坂城に蓄えてある鉄だけでは不足することがわかりました。
当時大籠(現岩手県藤沢町)では製鉄が盛んでしたがその指導をしたのは宇喜多藩から派遣された布留(のち千松と名乗る)大八郎・小八郎兄弟でした。
当時大籠は葛西氏の所領でしたが政宗と相談した宇喜多秀家は川村孫兵衛を同所に派遣することになりました。
孫兵衛は当時独身でした。そこで政宗公はキリシタンとして有名な豊後で北九州6か国を支配していた大友宗麟の重臣の娘、阿福(おふく)を嫁がせます。人質にしたのですね。
またこの時政宗公は孫兵衛に伊達藩の2人を家来として同行させています。
一人は画家、一人は測量士と推測します。
この2人に政宗公は阿武隈川から名取川までの絵図をつくれと命じ彼らには馬3頭を与えました。
案内役には仙台藩士大町清九郎を付け仙台藩へ送りました。
1596年暮れに孫兵衛は仙台藩に入りました。
岩沼に入ったときの通行手続きで孫兵衛は自分で名前を書いています。
そして大町清九郎に案内されて大籠に向かいます。
その後大籠から7回鉄を送っています。うち1回は大坂へ、6回は仙台城建設のため仙台藩へ。
仙台城築城場所選定でも孫兵衛が活躍
才能のあることを見抜いた政宗はこのほかに城を築くにはどこが良いか石巻と仙台を候補地に挙げ調べさせたのです。
政宗公の本命は石巻だったようですね。港に面した堺のように交易で栄えさせようという思いがあったのかもしれません。
孫兵衛はこれからの戦いは大砲があるから海に面したところではダメだと意見し、仙台の宮城野原と青葉山の2候補地に絞ったのです。

孫兵衛は政宗からの禄を断り名取郡早股村の谷地をもらいましたね
孫兵衛は政宗公から与えられる禄は仙台藩士が血を流して戦って与えられるものであり、もしもらっていたら妬みなどで今後の活動に支障が出ると考えたのかもしれません。
もう一つは開墾に自信があったのでしょう。阿部家の岩沼の先祖の土地も孫兵衛に与えられたのですよ。
孫兵衛の妻、阿福が人質を解かれ孫兵衛が伊達藩家臣になったのが1601年です。
孫兵衛はキリシタンだったのですか
そうです。孫兵衛は祖父の代からキリシタンでした。
熊谷元直も孫兵衛が向かった大籠の大八郎・小八郎兄弟もキリシタンです。
政宗は富国のために製鉄にも力を入れていました。
製鉄技術は西の方から来ましたがそれらの人はキリシタンが多かったのです。
後年キリシタン弾圧が起こったときに大量の処刑者がでたのも大籠です。製鉄とキリシタンは切れない縁がありますね。
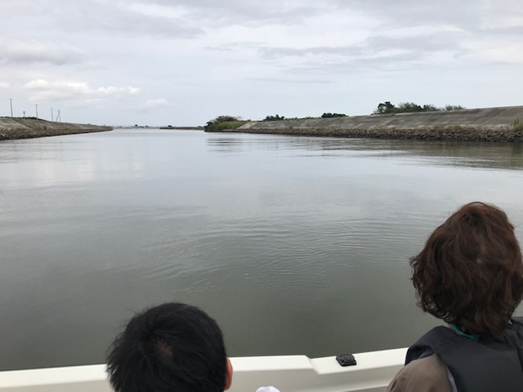
(↑ 現在の木曳堀 阿武隈川方面をのぞむ)
インタビューを終えて
川村孫兵衛と政宗公が出会ったのは1601年近江でと思っていましたがその前に伏見城再建現場で会っていたのですね。
正式に家臣になる1601年以前から孫兵衛は仙台藩に入っていたことも初めて知りました。
また、当時政宗公はキリシタンもかまわず重用していたというのも驚きでした。仙台藩の中には重臣も含めて相当なキリシタン藩士がいると思わせるものでした。
法人会員目標 200社 (現在31社)
個人会員目標 150名 (現在59名)
賛助会員 現在 6名